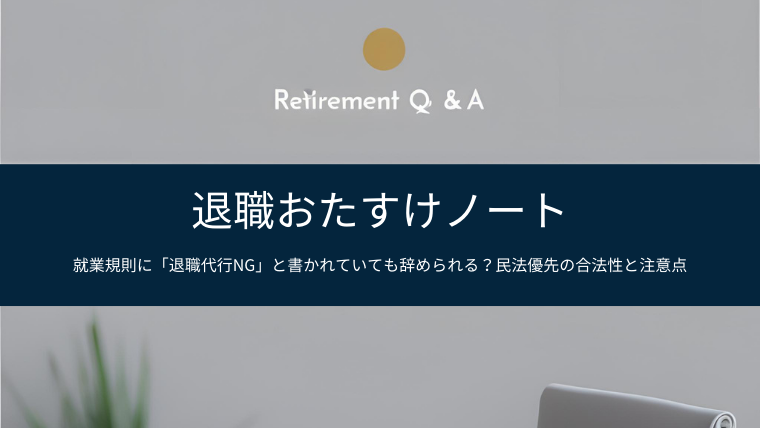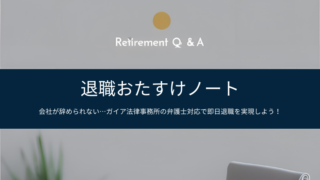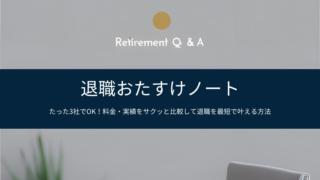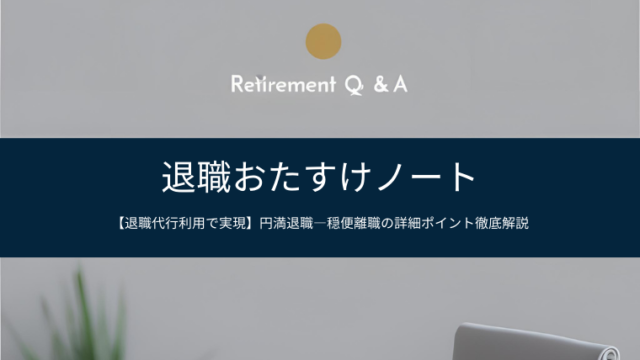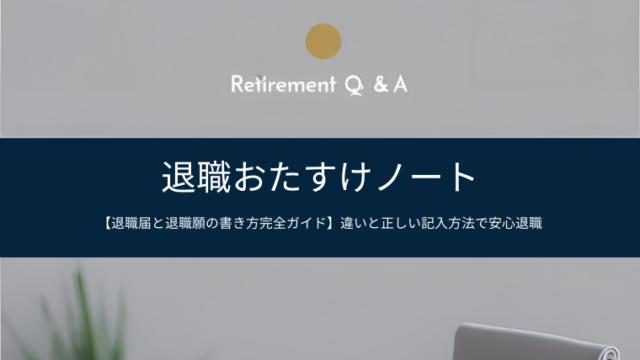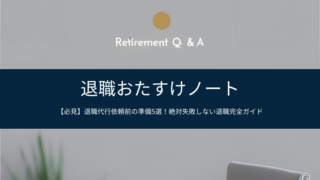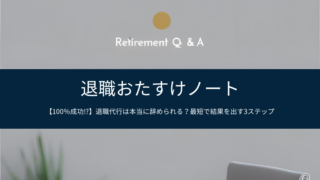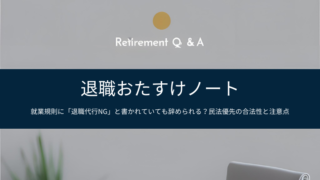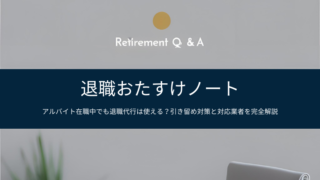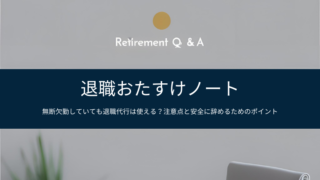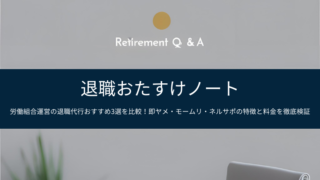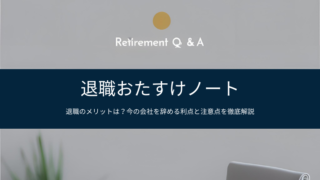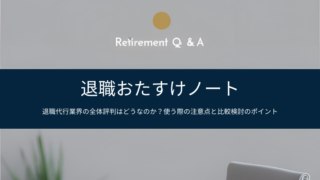退職しようと考える際、「就業規則に退職代行は禁止と書かれているから使えないのでは」と不安を感じたことはありませんか。
実は、退職に関しては民法が上位の法律となるため、社内ルールだけで辞める権利を縛ることはできないとされています。
本記事では、就業規則に「退職代行NG」と明記されていても問題なく辞められる理由と、その際の注意点をわかりやすく解説していきます。
安心して退職を進めたい方は最後までチェックしてみてください。
弁護士に任せて安心して退職したい人はこちら
就業規則より民法が優先されるため退職代行は使える
就業規則で「退職代行禁止」と記されていても、労働者が退職の自由を奪われるわけではありません。
なぜなら、法律の力が企業内の規定より強いからです。ここでは、民法に基づく退職の権利や、会社側がその権利を否定できない背景を確認しましょう。
退職は民法で保障される権利
労働契約は民法に根拠を持つ契約形態であり、就業規則はあくまで会社内部のルールにとどまります。
具体的には、民法627条 第1項により、期間の定めがない雇用契約の場合、労働者は14日前に申し出れば退職できるとされています。これが企業内規定に優先する点が重要です。
たとえ就業規則に「退職代行による離職は認めない」という文言があっても、法律で認められた退職意思を無効化することはできません。
民法という上位法によって、労働者の意思で退職できる自由が担保されているからです。
退職の自由が否定できない理由
会社側が「退職代行は規則違反だ」と主張したとしても、退職自体を止めるのは難しいといわれます。就業規則に違反したかどうかと、退職の有効性は別問題だからです。
たとえ会社が懲戒処分を検討したとしても、「辞めること」そのものを否定できるわけではありません。
実際の懲戒対象になるかどうかは、企業の就業規則の内容やその適用状況によって異なります。
ただし、退職を希望している人を強制的に働かせることは法律で制限されています。
退職代行を使ったからといって、結果的に退職が阻止されるわけではないのです。
就業規則違反が指摘されるケース
就業規則に「退職代行の利用禁止」が明記されていると、会社側がそれを根拠に引き留めを図る場合があります。
具体的にはどのようなトラブルに発展する可能性があるのか、知っておくと安心でしょう。
企業が就業規則を根拠に引き留めを図る可能性
就業規則に「直接の話し合いなしでの退職は認めない」といった文言があると、会社が「まずは本人が来て話し合うべきだ」と迫ることがあります。
こうしたやり方によって、退職意志を持つ従業員を慰留しようとするケースが見受けられるのです。
しかし、民法に基づいて退職の意思を伝える以上、企業側が「就業規則違反だから」という理由だけで辞められないとするのは難しいといえます。
引き留めが長引くと、退職自体が先延ばしになるリスクがあり、精神的な負担が増してしまう恐れもあるでしょう。
民事トラブルに発展しないための基本知識
仮に会社が「退職代行で辞めるなんて認めない」と強硬な態度を取ってきても、法的には労働者の退職を止める強制力はほとんどありません。
企業が従業員を損害賠償で訴えるには、実際に大きな損害が発生しているなどの特別な事情が必要です。
安心して辞めるためには、必要書類(離職票や源泉徴収票など)を事前に確認したり、退職代行業者と連携して連絡手段を整えたりしておくことが肝心です。
書類のやり取りをスムーズに行うことで、無用なトラブルを未然に防ぐことができるかもしれません。
なぜ合法性が認められるのか
ここまで、「就業規則にNGとあっても退職代行が使える」ことをお伝えしました。
では、具体的にどのような法的根拠に基づいて「合法性がある」とされているのか、もう少し詳しく見てみましょう。
民法の規定が上位法として効力を持つ
前述のとおり、就業規則は会社内部の規定であって、民法などの法律より優先することはできません。
民法が上位に存在し、それに矛盾する内容が就業規則に書かれていた場合、その部分は無効と判断される可能性があります。
実際に、過去の裁判例でも「法律に反する就業規則の内容は従業員に対して強制力を持たない」としたものがいくつも見られます。
つまり、会社が独自に「退職代行禁止」と決めても、法律に反する限り、それを根拠に退職を阻止することはできないと考えられます。
弁護士・労働組合など正当な代理権の存在
退職代行をめぐるトラブルで「違法ではないのか」と疑問を抱く方がいます。
しかし、弁護士や労働組合が運営する退職代行ならば、代理行為が正当に認められているため、法的にも問題なく対応できることが多いです。
特に弁護士運営のサービスであれば、代理権に基づいて会社との交渉が可能です。
労働組合の運営の場合でも、団体交渉という形で企業と交渉できるため、民法の上位法の枠組みをしっかり活かした退職手続きを進められるでしょう。
弁護士運営の退職代行を比較したい人はこちら
「退職代行NG」条項がある会社での例
就業規則に「退職代行禁止」がはっきりと書かれている企業でも、退職代行を利用して辞められる例を示します。
ここでは、2つの例を紹介し、どのようにして無事に退職へこぎつけたのかを見ていきます。
A社の場合
A社は就業規則に「退職代行の利用禁止」と明記しており、従業員は直接上司と話すよう定められていました。
しかし、ある従業員が精神的な負担を理由に退職代行業者へ相談し、会社へ通知を送ったところ、A社は退職を拒否することができませんでした。
その際、会社は「規定に反している」と主張したものの、労働者の退職の自由を法律で否定できないため、結果的には円満に退職が成立したのです。
しばらくは社内で不満の声が上がったものの、法的には従業員の意思を止められず、最終的に従業員の意志が尊重される形になりました。
B社の場合
B社も「退職代行で辞めることは禁止」と就業規則に書いていました。
しかし、従業員が弁護士運営の退職代行を活用したところ、会社は弁護士との連絡を通じて必要な書類をスムーズに用意することとなりました。
弁護士が「正当な代理人」として対応したため、B社は規定違反を理由に退職を阻止するのではなく、事務手続きを進めるしかなかったという経緯です。
結果的に、従業員は希望通りに退職でき、会社は法的な争いを避けるために円滑なやり取りを受け入れました。
弁護士運営の退職代行で安心
ここまでの例からわかるように、「退職代行はNG」と書かれていても、実際には辞められたケースが存在します。
とはいえ、トラブルを最小限に抑えるためには、弁護士運営の退職代行を選択するメリットが大きいといわれています。どのような理由で弁護士のサービスが有効なのか確認しましょう。
正当な代理行為が認められる理由
弁護士には、法律上の交渉権限があります。したがって、会社が「従業員ではなく第三者と話すのはおかしい」と主張しても、弁護士であれば問題なく対応可能です。
また、何かしら損害賠償などの話に発展しそうなときでも、弁護士が直接交渉できるため安心といえるでしょう。
さらに、就業規則に「退職代行は禁止」と書かれていても、弁護士運営の場合は違法行為に該当しません。
代理権を合法的に行使しているため、企業側も「規定違反」として従業員を罰するのが難しくなるわけです。
比較検討すべきポイント
弁護士が運営する退職代行を利用する際は、料金体系をあらかじめ確認することが大切です。着手金や成功報酬の有無、トラブルに発展したときの追加費用など、運営事務所によって幅があります。
無料相談を設けているサービスもあるため、まずは問い合わせてみるのが良いかもしれません。交渉実績や返金保証の有無なども比較して、自分の状況に合ったサービスを選ぶとスムーズに退職を進めやすいでしょう。
比較したい人はこちら